国債の価値と利回りの逆相関関係:わかりやすい仕組み解説
最近話題になっている、米国債の価値(価格)が下がると利回りが上がるという現象は、一見不思議に思えるかもしれませんが、実は非常にシンプルな仕組みで説明できます。この関係は「シーソー」のように、片方が上がれば片方が下がるという逆の動きをします。国債投資の基本原理を理解することで、なぜこのような現象が起こるのかを明確に把握することができます。
国債の基本的な仕組み
国債とは、国が投資家からお金を借りるために発行する借用書のようなものです。国債には「表面利率」というものが決められており、これは国が投資家に毎年支払う利息の割合を示しています。
例えば、表面利率が4%の国債であれば、100万円投資すると毎年4万円の利息がもらえることになります。
国債には「額面金額」というものがあり、これは満期になったときに必ず戻ってくる金額です。つまり、100万円の額面の国債であれば、何年後かの満期時には必ず100万円が戻ってきます。しかし、市場で取引される国債の価格は、この額面金額と必ずしも同じではありません。市場の状況によって、額面よりも高く売買されたり、安く売買されたりします。
この市場価格の変動が、利回りに大きな影響を与えます。
利回りとは、投資した金額に対して実際に得られる年間の収益率のことで、表面利率による利息収入だけでなく、売買による損益も含めて計算されます。
価格と利回りの逆相関メカニズム
国債価格が下落した場合の利回り上昇

国債の価格が下落すると利回りが上昇する理由を、具体例で説明してみましょう。
表面利率4%、額面100万円の国債があると仮定します。この国債を新発行時に100万円で購入した場合、毎年4万円の利息を受け取り、満期時には100万円が戻ってくるため、利回りは4%となります。
しかし、市場でこの国債の価格が90万円に下落したとします。この時点で90万円で購入した投資家を考えてみましょう。
この投資家は毎年4万円の利息を受け取り、満期時には100万円を受け取ります。つまり、90万円の投資に対して、毎年4万円の利息プラス満期時に10万円の差益を得ることになります。この場合の利回りは4%よりもかなり高くなります。

金利は固定されているから、価値が下がれば利回り上昇ってことか
利回り計算の基本式
今のアメリカ経済と国債暴落の実例
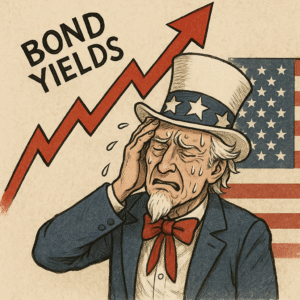
最近のアメリカ経済では、「国債が暴落している」現象が実際に起きています。
アメリカで何が起こったのか
-
2025年5月、アメリカ財務省が発行した20年国債の入札が不調に終わりました。これは「投資家があまり買いたがらなかった」ということです。その結果、国債の価格が下がり、利回り(投資家が得られる実質的な利益率)が上がりました。
-
このとき、アメリカの株価も下がり、ドルも売られるという「トリプル安」が発生しました。背景には「アメリカの財政が今後さらに悪化するのでは」という不安が広がったことがあります。
-
2025年4月には、株式市場の急落とともに、一時的に国債が買われて利回りが下がったものの、その後一転して国債も大量に売られ、10年国債の利回りが急上昇しました。これは「国債暴落」と呼べる現象です。
2025年のアメリカでは、国債の価格が大きく下落し、利回りが急上昇する「国債暴落」が起きています。背景には、財政赤字の拡大やトランプ政権による減税・関税政策への不安、そして国債の大量発行による需給悪化があります。

国債価格が下がると利回りが上がるため、政府が新たにお金を借りる(国債を発行する)ときのコストが大幅に上昇したんだ!!
誰のせいだ!!!!
実際、海外投資家などが国債を売却したことで、長期金利が急騰し、国債とドルが同時に下落する異例の事態となりました。このような動きは、アメリカの信用力低下や財政負担増加への懸念が強まっていることを示しています。

国債の価格が下がると利回りが上がる仕組みも、こうした実例を見ることでより理解しやすくなります。
結論
国債の価値が下がると利回りが上がる仕組みは、固定された表面利率と変動する市場価格の関係によって生まれます。国債の表面利率は発行時に決定され満期まで変わりませんが、市場価格は常に変動しています。
価格が下落すれば、同じ利息収入と同じ満期償還金額に対して、より少ない投資額で済むため、実質的な利回りが向上します。
この関係を理解することは、国債投資だけでなく、金融市場全体の動きを把握する上で非常に重要です。金利環境の変化が国債価格にどのような影響を与え、それが投資家の実質的な収益率にどう反映されるかを知ることで、より適切な投資判断ができるようになります。
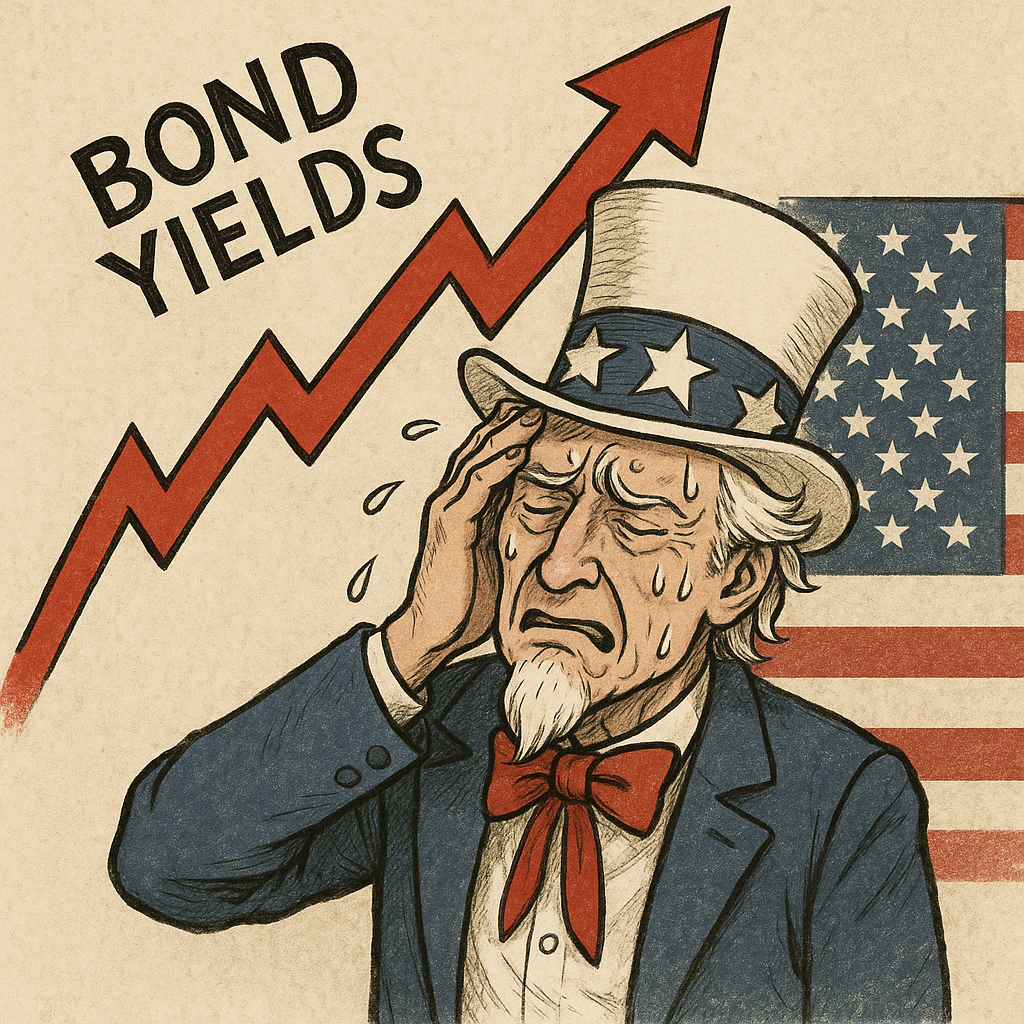


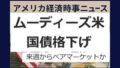

コメント