5月1日の日銀会合で利上げの可能性はあるのか
2025年3月の金融政策決定会合で現状維持を決定した日本銀行ですが、5月の次回会合での利上げ観測が急速に高まっています。植田和男総裁が「4月初め」や「次回会合」でトランプ関税の影響を評価できると発言したことや、春季労使交渉での高い賃上げ率が確認されたことから、市場では従来の「半年に一度」という利上げペースが加速する可能性が指摘されています。金利スワップ市場では5月利上げ確率は24%と見積もられており、物価上昇の持続性や円安リスクへの対応が鍵となります。本稿では、日銀が5月に利上げを実施する可能性について、経済指標や金融環境の分析を踏まえて詳細に検討します。
現在の金融政策状況と市場の見方
3月会合での現状維持決定とその背景
日本銀行は2025年3月19日に開催した金融政策決定会合において、市場予想通り政策金利である無担保コール翌日物金利の誘導目標を0.5%に据え置く決定を行いました。
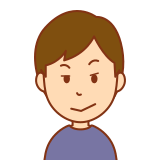
発表は11時30分にされ、いつもよりかなり早い時間だったな。
この決定は政策委員全員一致で採択され、日銀は「一部に弱めの動きもみられるが、緩やかに回復している」と日本経済を評価しています。
植田総裁は会合後の記者会見で
と利上げ継続の方針を明確に示しました。
利上げペースの現状と市場予想
これまで日銀は2024年3月、同7月、2025年1月と「半年に一度」のペースで利上げを実施してきました。
市場の見方では、この利上げペースが維持されるなら次回は7月の可能性が高いはずですが、金利スワップ市場から試算される利上げ確率は
5月が24%、6月が31%、7月が26%と、従来のペースよりも早期の利上げ観測が強まっています。
特に注目すべきは、5月に利上げが実施された場合、これまでの「半年に一度」というパターンから「倍速利上げ」へと転換することを意味する点です。
引用先:https://www.mizuho-rt.co.jp/publication/executive/pdf/km_c250324.pdf
5月利上げの可能性を高める要因
高水準の物価上昇率
2025年2月の生鮮食品を除く総合指数(コアCPI)は前年比3.0%上昇しており、3ヶ月連続で3%台の上昇率となっています。
特に、食料(生鮮食品除く)は前年比5.6%上昇し、米類に至っては前年比80.9%という大幅な上昇を記録しています。将来の見通しについても、2025年度のコアCPIは前年度比2.3%上昇と予測されており、日銀の目標である2%を上回る水準が続く見込みです。このような持続的な物価上昇は、日銀が金融引き締めを加速させる要因となり得ます。
春季労使交渉の高い賃上げ実績
2025年の春季労使交渉における第1回回答の集計では、賃上げ率が平均5.46%となりました。
この結果について植田総裁は「オントラック(想定通り)の中でもやや強め」と評価しており、物価上昇を賃金上昇が支える好循環の形成を確認したと言えます。この高い賃上げ実績は、日銀が目指す「物価安定の目標と整合的な物価上昇の持続」に向けた重要な条件の一つが満たされつつあることを示しています。
トランプ関税政策の影響評価
植田総裁は記者会見で、トランプ政権の通商政策について「4月初めには通商政策の内容がある程度出てくる。次回の決定会合ないし展望リポートの中である程度消化できる」と述べています。
このように、次回会合までに重要な不確実性要因が一定程度明確化される見通しであることも、5月利上げの可能性を高める要因となっています。
5月利上げに慎重な見方
従来のペースとの乖離
日銀の利上げペースは「半年に一度」という比較的慎重なものでした。急に「倍速利上げ」に転じることは、市場に過度なショックを与える可能性があります。みずほリサーチ&テクノロジーズのエグゼクティブエコノミスト門間一夫氏のレポートでは「5月利上げはありえないように思える」としながらも、「植田総裁はその可能性を全否定はしなかった」と指摘しています。引用先:https://www.mizuho-rt.co.jp/publication/executive/pdf/km_c250324.pdf
経済の脆弱性への懸念
2024年第4四半期のGDPは前期比0.6%増加し、年率換算では2.2%成長となり3四半期連続のプラス成長を記録しましたが、輸入の減少が成長率を押し上げた一方で内需は弱含みでした。2024年の実質GDP成長率は-0.1%とG7諸国で最低となる見通しであり、この経済の脆弱性は急速な金融引き締めに対する慎重論の根拠となっています。
国際金融情勢の不確実性
トランプ政権の通商政策に関する不確実性が依然として高い状況は、日銀が早急に次の利上げ時期や今後の利上げペースに関する明確な指針を示すことを難しくしています。
また、FRBの利下げ見通しもあり、国際金融環境の変化が日本の金融政策にも影響を与える可能性があります。
市場の反応と専門家の見解
異なる利上げ時期予測
野村證券では、日銀は「25年7月と26年1月に0.25%ポイントずつ利上げを実施し、政策金利を1.0%まで引き上げる」と予想していますが、一方で「市場の一部では早ければ次回(4月30日~5月1日)の決定会合で利上げとの見方も高まっている」と指摘しています。
これは、市場参加者の間でも見方が分かれていることを示しています。
政策金利の最終着地点に関する見解
植田総裁は中立金利(景気に対し緩和的でも引き締め的でもない金利水準)を「1.0~2.5%程度」と幅広く見ており、日銀内で最もタカ派的(利上げに積極的)と見られる田村審議委員は「2025年度後半までに、最低でも1.0%程度への利上げが必要」と発言しています。
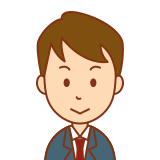
この発言はかなりタカ派な発言ですね。
これらの見解は、日銀が今後も段階的に利上げを続ける意向を持っていることを示唆しており、その過程で5月利上げの可能性も排除できないことを示しています。
為替市場への影響と利上げ決断の関係
円高傾向と日米金利差
2025年3月25日時点の米ドル/円レートは151.95/149.70(TTS/TTB)となっており、2025年に入って以降、円高傾向が進行しています。この背景には、FRBの利下げと日銀の利上げという日米金利差の縮小予想があります。複数の金融機関が2025年末までに円高が進むと予測しており、その範囲は140円台前半から153円程度とされています。
為替動向と金融政策の関連性
2025年1月の日銀利上げ決定時にも円安是正が動機の一つだったことが示されています。為替動向は金融政策判断の重要な要素となっており、急激な円安が進行した場合には、それを是正する目的で5月の利上げが正当化される可能性もあります。ただし、現状では円高傾向にあることから、為替要因だけで5月利上げが促される可能性は低いと考えられます。
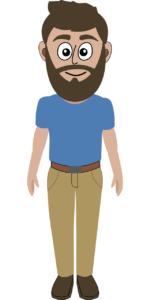
円安是正のための利上げも1年遅かったとも言われています。
まとめ:5月利上げの実現可能性と今後の展望
日銀が5月に利上げを実施する可能性は、3月会合前と比較して明らかに高まっています。特に、植田総裁の「次回会合までにトランプ関税の影響を評価できる」という発言や、春季労使交渉での高い賃上げ率の実現は、5月利上げのシナリオを現実味のあるものにしています。
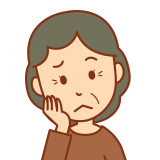
アメリカの関税政策が大きく左右するのかしら・・・
しかし一方で、日銀の従来の慎重な利上げペースからの急激な転換には懸念も残ります。金利スワップ市場から導き出される5月利上げの確率が24%とされていることからも、市場全体としては6月以降の利上げをより可能性が高いと見ていると言えます。
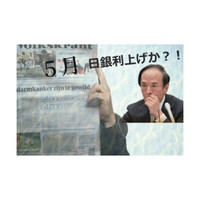
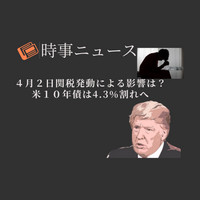

コメント